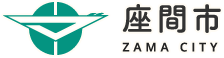想い出の座間 人々の経済生活編
「想い出の座間」は、書籍の「目で見る座間」をホームページに忠実に反映することを基本にしています。
今回は、前回の昭和前期に続き、人々の経済生活を紹介します。内容は、屋敷がまえ、米ができるまで、麦作、畑地灌漑事業、養蚕、養種製造、野良着姿、他の生業に関する写真とコメントになります。
ダイジェスト版
全体は添付ファイルに掲載しています。内容は、屋敷がまえ、米ができるまで、麦作、畑地灌漑事業、養蚕、養種製造、野良着姿、他の生業に関する写真とコメントです。

この辺では、母屋や庭など日常生活に必要な施設のある敷地をヤシキ(屋敷)と呼ぶ。母屋はほとんど東か西向きに建てられ、その前面に広く庭を取り、庭を囲むように物置などの付属建物が建っており、それらの建物は草屋根がほとんどであった。ヤシキの囲りには防風などのため、屋敷林やクネガキ(垣根)を植えている。
草葺屋根
市内には草葺の家は姿を消してしまった。写真は上栗原。

座間の農業は大まかにいって、西部の田場所と呼ばれる水田地帯と東部のオ力場所、ノヤと呼ばれる畑作地帯とに分けられる。
苗ふり 4月の下旬になると苗代作りが行われる。苗代にする田は水の調整に便利で土質が良い所を選び、ていねいに代をかいた。
ここへ5月の3、4日ごろ苗ふりといって種籾を播く。

田んぼで干された稲は、自宅の庭へ運んでから脱穀された。昭和31年11月。

養蚕は蚕種を蚕種商から買って、これを孵化させて行うが、この蚕種は初め長野、群馬、栃木などの業者から買われていたが、明治末から大正時代にかけ市内にも上宿に大盛館、中宿に精業館、新田宿に香川などの大きな蚕種製造業者ができ、県下に名を知られた。
写真は座間中宿の精業館。

「高座豚」の名前があるように、この地方の養豚の歴史は古い。座間でも大正初期から種豚を中心に盛んに飼育され、現在に至っている。

戦後の日本農業の出発点となった農地改革の終了を記念して、昭和23年4月、座間小学校運動場で農地祭が行われた。写真は改革に当たった農地委員の人々。
以上はダイジェストとして掲載したものです。全体については以下の添付ファイルをご覧下さい。
-
想い出の座間 (人々の経済生活編) (PDF 18.9 MB)

想い出の座間、人々の経済生活編の写真とコメントです。
(2025年9月19日作成)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生涯学習課 文化財担当
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8431 ファクス番号:046-252-4311
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。