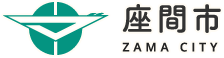アライグマには要注意
アライグマには要注意
特定外来生物「アライグマ」の目撃情報が、座間市内でも増加しております。
可愛らしい見た目に反してとても凶暴な動物のため、むやみに近づくと噛みつかれたり、引っかかれたりするおそれがあります。アライグマを見かけても絶対に近づいたりしないでください。
アライグマを見かけたら…
路上や庭などでアライグマを見かけた場合、見かけた人は驚くかもしれませんが、多くの場合、アライグマの方が逃げていくはずです。ただし、むやみに近づいたり、触ったりしようとすると噛まれたり、引っかかれたりするおそれがあります。また、感染症を媒介するおそれもありますので、絶対に近づかないでください。また、見た目が可愛いからといって、食べ物を与えないでください。
アライグマの特徴
アライグマは中型の哺乳類で、タヌキやアナグマに似ていますが、頭胴長40~60cm、体重は4~10数kg程度とタヌキよりも一回り大きいことと、尻尾が長く、白黒の縞模様になっているのが特徴的です。


尻尾の縞模様が特徴的です。
アライグマの生態
| 繁殖 |
国内では、通常、春に、1回、1~7匹程度を出産するといわれています。ただし、春の繁殖が失敗した場合、夏から秋に再度出産することもあるといわれています。 |
|---|---|
| 食性 | 雑食性で、野外に定着した個体は、果実・野菜・穀類、小動物・鳥類・両生類・爬虫類・魚類・昆虫などの小動物全般を採取するといわれています。 |
| 生息環境 | 河川周辺など、水辺の環境を好みますが、森林、農地、市街地など、幅広い環境に生息します。 |
| 行動 | 基本的に夜行性ですが、日中も活動します。基本的に単独行動とされていますが、高密度の地域では複数で行動することもあるようです。また、木登りや泳ぎが得意です。 |
アライグマに関する主な人獣共通感染症
アライグマに関する主な人獣共通感染症の概要です。
| 狂犬病 | 狂犬病ウイルスによる感染症で、全ての哺乳類に感染します。感染した動物に噛まれたり、引っかかれたり、傷口を舐められたりすることにより感染します。 なお、日本国内では昭和32年以降、狂犬病の発症例はありません。 |
|---|---|
| レプトスピラ症 | 細菌による感染症で、イヌやネズミなど、多くの哺乳類に感染します。レプトスピラ菌に感染した動物の尿や尿に汚染された水、土壌から、皮膚、粘膜表面の創傷などを通じて人に感染します。また、レプトスピラ菌に汚染した食物からも感染します。 感染した場合、初期症状として、発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、結膜充血などがあり、重症の場合は、黄疸、出血、腎機能障害などの症状が認められることもあります。 |
| アライグマ回虫症 | アライグマ回虫はアライグマの小腸に寄生し、アライグマに対しては病原性を示しません。成虫は1日10万個超の卵を産み、糞便を通して体外へ排出されます。人への感染は、アライグマの糞で汚染された土壌その他を経口的に摂取することにより生じます。 なお、日本では平成14年10月時点では、野生のアライグマ回虫の寄生例は確認されておりません。また、人への感染事例も確認されていないといわれています。 |
| アライグマ糞線虫症 |
アライグマ糞線虫は、アライグマの小腸の粘膜上皮に潜り込んで寄生する長さ2~3mm程度の線虫です。幼虫の多くが便とともに体外へ排出され、フィラリア型幼虫となって土壌や水中にとどまり、経皮感染により人やその他の哺乳類の体内に入り込みます。 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 平成23年に中国で報告されたSFTSウイルスによる感染症で、日本では平成24年に初めて患者が確認されました。主に、SFTSウイルスを保有するマダニに刺されることで感染しますが、SFTSを発症している動物との接触によって感染することもあるといわれています。 アライグマもSFTSウイルスを媒介するマダニを運搬し、または糞便中に直接ウイルスを排出する可能性があるといわれています。 人が感染した場合、突然の発熱、下痢や下血など消化器症状、血小板および白血球減少がみられ、死に至る場合もあります。令和7年には、神奈川県内での感染事例もありました。 |
アライグマによる被害を防ぐためには
エサとなるものをなくす対策事例
庭木や家庭菜園などは適切に管理して、果実などエサになるものを残したままにしない。
ペットのエサの食べ残し、お墓の供え物などを野外に放置しない。
池や屋外の水槽で魚などを飼育している場合、金網などで覆い、食べられないようにする。
など…
繁殖場所をなくす対策事例
家屋へ侵入されないように、破損箇所などの入口になりそうな箇所は塞いでおく。
空き家、倉庫、物置などは定期的に点検・清掃し、棲みつかれないようにする。
など…
アライグマなどによる被害があった場合
アライグマは特定外来生物ではありますが、無断で捕獲することは法律で禁止されています。また、具体的な被害がなく、目撃情報だけでは捕獲を行うことはできません。自宅の庭木の果実を食べられるなど、アライグマなどによる被害があった場合、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)に基づき、捕獲の許可をしています。捕獲の許可についてはページ下部の関連情報のリンクを参照してください。また、捕獲檻(箱罠)の貸出も行っておりますが、数量、貸出期間などに限りがあります。詳しくは担当までお問い合わせください。
なお、天井裏や床下などへ入り込まれてしまった場合には、業者へ駆除を依頼するなどしてください(費用は自己負担となります)。また、市からは特定の業者を紹介、あっせんなどはできませんので、公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会(電話番号:045-681-8585)などへお問い合わせください。
参考情報等について
このページは「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)(令和7年3月改訂版)」等を元に作成いたしました。アライグマ等について、詳しくお知りになりたい場合は、以下のリンクなどを参照してください。
-
アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)(外部リンク)

-
防除の公示(アライグマ)(外部リンク)

第4次神奈川県アライグマ防除実施計画 -
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について(外部リンク)

-
動物由来感染症を知っていますか?(外部リンク)

-
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)患者の発生に伴う注意喚起について(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ
クリーンセンター クリーン活動係
〒252-0029 座間市入谷西二丁目52番14号
電話番号:046-252-8724 ファクス番号:046-252-7641
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。