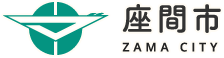病気やけがで障がいが残った際はご相談を 障害基礎年金制度
障害年金は、病気やけがにより初めて医師の診察を受けた時(初診日)加入していた年金制度により、障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金(厚生年金)、障害共済年金(共済年金)の三種類に分かれます。そのうち、市役所で相談・受け付けをしているのは障害基礎年金※です。
障害基礎年金は、以下の受給要件を満たす方が一定以上の障がい状態にある間支給される年金です。
障害厚生年金、障害共済年金の相談・請求先は、それぞれ年金事務所や各共済組合です。
※初診日に第3号被保険者(会社員、公務員等の扶養配偶者)である場合は、年金事務所での相談・受け付けとなります。
対象
次の1~3の全ての要件を満たす方
- 障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます)
- 障がいの程度が、障害認定日(原則初診日から1年6カ月を経過した日、傷病などにより異なる場合があります)または20歳に達したときにおいて、国民年金法の障害等級基準を満たしていること(障害者手帳の等級とは基準が異なります)
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、保険料の未納期間が3分の1を超えないこと。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年3月31日までの特例)
※「初診日」とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日のことをいいます。
※「障害認定日」とは、障がいの程度を定める日のことで、原則初診日から1年6カ月を経過した日のことをいいます。ただし、1年6カ月以内に症状が固定した場合はその日が障害認定日とみなされます。
20歳前の傷病
20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害等級基準を満たしていれば支給対象になります。
※本人の所得額によっては一部、または全額が支給停止される場合があります。
事後重症制度
障害認定日においては、障がいの程度が軽く、障害基礎年金が支給されない場合でも、その後障がいが重くなり、65歳に達する日の前までに障害等級基準を満たすようになったときは支給対象になります。
※65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。また、年金を繰り上げ受給していると申請できない場合があります。
金額
令和7年度の金額
- 1級:年額1,039,625円
- 2級:年額831,700円
子の加算額(※)
- 1人目、2人目:それぞれ年額239,300円
- 3人目以降:それぞれ年額79,800円
※生計を維持している子(18歳に到達する年度末までの子、1・2級の障がいのある20歳未満の子)がいる時は加算されます。
請求に必要となるもの
請求者の年金加入歴や病歴などに応じて必要なものが異なるため、保険年金課、または年金事務所までお問い合わせください。
受付時間(市役所)
障害年金の相談や申請受付は予約制です。詳しくは、下記リンク「障害基礎年金相談の予約制導入」をご覧ください。
平日(月曜日~金曜日)の9時~11時、14時~16時
問い合わせ先
厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)
詳しくは、下記関連情報「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。