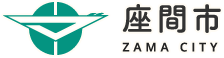救命の連鎖の重要性と1次救命処置
救命の連鎖の重要性
心肺停止の傷病者の救命や機能回復のためには、その場に居合わせた方(バイスタンダー)が、早期に119番通報および心肺蘇生法を開始し、救急隊が必要な救急救命処置を行い医療機関へ搬送し医師の治療が行われます。
この一連の流れが円滑に進んだとき、傷病者の救命が可能となります。
これを「救命の連鎖(れんさ)」といいます。

心停止の予防;突然死の可能性のある傷病を未然に防ぐこと。小児では交通事故、不慮の事故などを防ぎ、成人では心疾患や脳卒中などの兆候を見逃さないこと。
早期認識と通報;突然倒れたり反応がない人を見つけたら心停止を疑うこと。判断に迷っても、大声で応援を呼び、119通報とAEDの搬送を依頼します。
一次救命処置;その場に居合わせた方がすぐに行える処置であり、心肺蘇生など社会復帰に大きな役割を果たします。
二次救命処置;救急救命士や医師が薬や器具を使い心拍の再開を目指し、再開後に集中治療を受け、リハビリテーションなどを経て社会復帰を目指します。
4つの輪のうち1つでも途切れれば救命の効果は低下します。
心肺蘇生法
心肺蘇生法とは、意識が無く、心臓の動きもなく、普段通りの呼吸も感じられないと判断した傷病者(以下傷病者)に、胸骨圧迫(心臓マッサージ)と人工呼吸を実施します。これは生命を維持するための循環を保つために行います。また、心臓の動きや呼吸を取り戻すだけではなく、脳の機能を守り傷病者の社会復帰を目指すものでもあります。

脳は、酸素を大量に使用する臓器です。脳は酸素が送られなくなってから3分以上継続すると、脳機能に障害が発生してきます。脳機能は一度障害をおうと再生することはないため、心肺蘇生を行い早期に酸素を脳に送ることが極めて重要となります。
救急車が皆さんのところに到着するのに全国平均で約10分掛かります。脳の機能が障害を受けるまでの時間は約3分といわれているので、救急車が到着するまでに空白の10分間が出来てしまいます。この10分間を皆さんにうめてもらうことで、救命の連鎖(れんさ)がスタートします。
心肺蘇生法を行うにあたって、まず傷病者を「観察」「判断」し、適切な手順に従って手当てをする必要があります。
AEDによる電気ショックの適応ではない不整脈もあります。また、いつも身近な所にAEDがあるとは限りません。
AEDが到着するまで、または救急隊に引き継ぐまでは、十分な強さ、速さ、絶え間ない心肺蘇生法が必要です。
詳しい手順などに関しては、下記の関連情報の「心肺蘇生法の手順」を参照してください。
また、AEDの使用に関しては下記の関連情報の「AED(自動体外式除細動器)」を参照してください。
気道異物除去
気道異物除去とは気道(空気の通り道)に何らかの異物(食物・痰など)が詰まり、呼吸ができない窒息状態を疑った際に行う救命処置です。
居合わせた方は、まず「咳」をさせ、大声で応援を呼び、119番通報とAED搬送を依頼します。
異物が出なければ、肩甲骨と肩甲骨の間を「手のひらの付け根」で叩きます。

このページに関するお問い合わせ
消防署消防管理課 消防管理係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2214 ファクス番号:046-256-2215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。