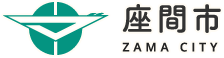認知症対応型共同生活介護事業所における協力医療機関との連携に係る届出書
届出の趣旨
令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を、指定権者である市町村長に届出なければなりません。
なお、これとは別に、協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに指定権者である市町村長に届出をしてください。
届出の様式
届出は、「(別紙3)協力医療機関に関する届出書」を使用してください。
「(別紙3)協力医療機関に関する届出書」は、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」の「基準省令に関する通知(解釈通知)」に掲載されています。
当該ページは、次に記載されている外部リンクからアクセスすることができます。
協力医療機関の要件
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければなりません。
協力医療機関を定めるに当たっては、次の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めてください。
- 利用者の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
- 認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
- 協力医療機関および協力歯科医療機関は、共同生活住居から近距離にあることが望ましいです。
- 連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診察所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関等の在宅医療を支援する地域の医療機関(以下、在宅療養支援病院等)と連携を行うことが想定されています。
- なお、令和6年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、在宅療養支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれませんので、御留意ください。
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)である病院または診療所との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症または同条第九項に規定する新感染症をいう。以下同じ)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなりません。
取り決めの内容は、流行初期期間経過後(新興感染症の発生の公表後4か月程度から6か月程度経過後)において、指定認知症対応型共同生活介護事業所の入居者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の可否の判断、入院調整等を行うことが想定されます。
なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではありません。
協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合
協力医療機関が第二種協定医療機関である場合には、入居者の急変時等における対応の確認と合わせ、当該協力期間との間で、新興感染症の発生時等における対応について協議を行わなければなりません。
協議の結果、当該協力医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えられますが、協力医療機関のように日頃から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが望ましいです。
医療機関に入院した入居者の退院後の受け入れ
利用者が協力医療機関その他医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合は、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所へ速やかに入居させることができるよう努めなければなりません。
なお、必ずしも退院後に再び入居を希望する入居者のために常に居室を確保しておくということではありません。
その他の協力・連携の体制
- あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければなりません。
- サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等とのバックアップ施設との間の連携および支援の体制を整えなければなりません。
これらの協力医療機関やバックアップ施設から、利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、当該医療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものです。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。