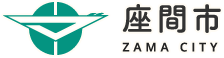令和7年度の介護保険料
介護が必要な人を社会全体で支える介護保険制度について、令和7年度の介護保険料をお知らせします。
65歳以上の方の介護保険料額
介護保険料は、3年に一度見直しを行います。令和6年度~8年度の3年間、市で必要な介護サービスの費用を賄えるよう、介護サービスの利用者と利用量の増加などを考慮しながら基準額を決定しました。
市内在住の65歳以上の方(第一号被保険者)の保険料基準額は、年額70,300円となります。実際に納付する保険料は、この基準額を基に、それぞれの所得段階に応じて20段階に分かれています(表1参照)。所得段階は、毎年度本人の前年中の収入や所得に応じて(本人が非課税の方は、世帯の課税状況も勘案されます)決定します。
なお、保険料の年額および納付方法については、6月中旬にお送りする介護保険料額決定通知書でお知らせします。
※令和7年4月から、第1・第2段階、第4・第5段階を区分する基準となる金額が、「80万円」から「80万9千円」に変わりました。
低所得者の保険料軽減
所得段階が第1段階~第3段階の方については、低所得者対策として消費税を財源として公費が投入され、保険料が軽減されています。
|
段階 |
対象者 |
保険料(年額) |
|---|---|---|
|
1 |
|
20,030円 |
|
2 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額(年金所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万9千円を超え、120万円以下の方 ※低所得者対策として、消費税を財源として公費が投入され、割合が0.2軽減されています。 |
34,090円 (基準額(円)×0.485) |
|
3 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額(年金所得を除く)と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 ※低所得者対策として、消費税を財源として公費が投入され、割合が0.005軽減されています。 |
48,150円 (基準額(円)×0.685) |
|
4 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の合計所得金額(年金所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の方 | 63,270円 (基準額(円)×0.90) |
|
5 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の合計所得金額(年金所得を除く)と課税年金収入額の合計が80万9千円を超える方 | 70,300円 (基準額(円)×1.00) |
|
6 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120万円未満の方 |
84,360円 (基準額(円)×1.20) |
|
7 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 |
91,390円 (基準額(円)×1.30) |
|
8 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 |
105,450円 (基準額(円)×1.50) |
|
9 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 320万円以上420万円未満の方 |
119,510円 (基準額(円)×1.70) |
|
10 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 420万円以上520万円未満の方 |
133,570円 (基準額(円)×1.90) |
|
11 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 520万円以上620万円未満の方 |
147,630円 (基準額(円)×2.10) |
|
12 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 620万円以上720万円未満の方 |
161,690円 (基準額(円)×2.30) |
|
13 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 720万円以上800万円未満の方 |
168,720円 (基準額(円)×2.40) |
|
14 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 800万円以上900万円未満の方 |
175,750円 (基準額(円)×2.50) |
|
15 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 900万円以上1,000万円未満の方 |
182,780円 |
|
16 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 1,000万円以上1,100万円未満の方 |
189,810円 |
|
17 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 1,100万円以上1,200万円未満の方 |
196,840円 (基準額(円)×2.80) |
|
18 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 1,200万円以上1,300万円未満の方 |
203,870円 (基準額(円)×2.90) |
|
19 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 1,300万円以上1,400万円未満の方 |
210,900円 (基準額(円)×3.00) |
|
20 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 1,400万円以上の方 |
217,930円 (基準額(円)×3.10) |
「合計所得金額」とは
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除し、分離課税の長(短)期譲渡所得の特別控除(土地・建物に限る)を適用した金額となります。
なお、扶養控除や医療費控除などの所得控除を適用する前の金額となります。
- 第1段階から第5段階の人について、合計所得金額(公的年金などに係る雑所得を除く)に「給与所得」が含まれている場合は、「給与所得額(所得金額調整控除前)」から最大10万円控除します。
介護保険料の納付方法
介護保険料の納付方法は2通りあります。年金からの差引き(特別徴収)が原則となりますが、年金受給状況により納付書払いや口座振替(普通徴収)となります。
- 特別徴収では、年間の年金受給額が18万円以上の方は年金から差引きでの納付となります。対象となる年金は老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金です。
- 普通徴収では、市からお送りする納付書または口座振替でのお支払いとなり、1年間分を10回に分けて6月から納付します。対象となる方は、65歳になられたばかりの方、転入された方、差し引き対象の年金を受給されていない方、年間の年金受給額が18万円未満の方です。
なお、普通徴収から特別徴収に切り替わる場合、市からお知らせをお送りします。また、年度の途中で特別徴収が開始となる方や介護保険料が増額となる方は、一時的に特別徴収と普通徴収を併用しての納付(併用徴収)となる場合があります。
特別徴収の方の「仮徴収」
介護保険料は、所得段階別に設定されるため、各年度の保険料額は、前年度の所得が決定する6月以降に算定します。このため、すでに保険料を年金から差し引きされていた方は4月、6月、8月は確定した保険料での年金差し引きができないため、令和7年2月の保険料と同額が差し引き(仮徴収)されます(8月の金額は調整される場合があります)。令和7年度の保険料の決定後、仮徴収合計額を減じた額が10月、12月、2月に分けて差し引き(本徴収)されます(表2参照)。
表2 特別徴収の仮徴収と本徴収(令和7年度)
- 仮徴収
-
4月・6月・8月(令和7年2月の保険料と同額)
- 本徴収
- 10月・12月・2月(年額保険料から仮徴収額を引いた金額)
納付が困難な方へ
市では、生活が著しく困難と認められた方(前年中の収入が、生活保護基準以下であることなど)に対して、介護保険料を減免する制度を設けています。詳しくは、担当へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。