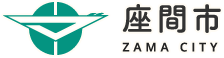大凧ができるまで
骨組みの様子

大凧の概要
- 大きさ
- 13m四方
- 糸目
- 47本、70m
- 引き綱
- 200m
- 尾の長さ
- 約80m
- 総重量
- 約1,000kg
- 凧上げに必要な人員
- 100人以上
- 凧上げに必要な風速
- 10~15m
13メートルの凧が揚がるにはたくさんの工夫が必要
「大凧まつり」はかながわのまつり50選にも選ばれています。この大凧を作っているのは、市の大凧保存会の人たちです。大凧作りの作業は、骨組み、紙張り・縄入れ、文字書き、糸目付けに分けられ、この順で進められます。凧ができあがるまでには、約2カ月間かかります。
(1)骨組み
骨組みに使う竹は、太さ約8センチから10センチの男竹と女竹で、軽く弾力を増すため、切ってからしばらくたったものを使います。使う本数は約150本、まるごと一本の竹や、割った竹を麻縄やわら縄で結び組んでいきます。
(2)紙張り・縄入れ
使われる紙は凧用の特別な手すき和紙、新聞を開いたくらいの大きさで、全部で250枚使います。この和紙を、縦1.7m、横6.6mのものを16枚作ります。そして16枚の紙の四隅に約1センチの太さの縄を入れノリで張ります。
(3)文字書き
体育館に16枚の紙を並べ、小さな見本を見ながら書きます。座間の大凧の特徴の一つに、字凧であるということが挙げられます。右上に赤色で太陽を、左下に緑色で大地を表す二文字が書かれます。文字は、約200年の歴史をもつ大凧まつりを、より身近なものにしていただこうと、毎年広く市内外の皆さんから募集して決めています。
(4)糸目付け
凧が揚がるかは糸目付けで決まるといわれるほど大切です。そこで、根気と時間をかけ47本の糸目を付けます。糸目はロープで太さが約1センチもあり、凧が空で前傾に、しかも左右の下側の糸にたるみをもたせるように付けます。
このページに関するお問い合わせ
地域プロモーション課 観光・交流係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8003 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。