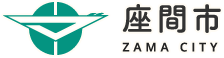予防接種(乳幼児・小学生)
麻しん風しんの定期予防接種期間の延長
麻しん・風しんを防ぐ混合ワクチン(MRワクチン)定期接種の接種期間が令和6年度末で終了する方について、ワクチンの供給不足により令和6年度中に接種できなかった場合、定期接種の期間が2年間延長されます。
定期予防接種
全ての定期予防接種を、指定医療機関で個別接種にて実施しています(令和3年4月1日から、BCGも指定医療機関での個別接種になりました)。
乳幼児の予防接種の個別通知はしていません。出生の方には、予防接種の案内を個別通知しています。
小学校時に行う予防接種は、個別通知を実施しています。
対象は、接種時に市に住民票があり該当する予防接種の対象年齢である子どもです(麻しんまたは風しんにかかった人も、麻しん風しん混合の予防接種が可能です)。
費用は無料です(ただし、1~3の人は予防接種は受けられません。4~6の人は有料接種となります)。
- 予防接種と子どもの健康で「予防接種を受けることができない場合」に該当する人。
- 麻しん風しん両方にかかった人(疑わしい人は、医師と相談して接種してください)。
- 麻しん、風しん、おたふくかぜ、水ぼうそう、突発性発疹、りんご病、手足口病の治癒後2~4週間経っていない人(麻しんの場合は4週間以上)。
- 定められた接種間隔以外で接種した人。接種間隔は、それぞれの説明をご覧ください。
※定められた接種間隔より短い間隔で接種した場合は自費の扱いとなります。 - 指定医療機関以外で接種をした人。
- 法律による対象年齢外の人(ただし、市の日本脳炎の接種開始年齢は3歳からです)。
持参するもの
母子健康手帳、マイナ保険証または健康保険証
各予防接種
ロタウイルスワクチン、小児肺炎球菌、B型肝炎ワクチン、5種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)、4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)、ヒブワクチン、BCG、麻しん・風しん、水痘(水ぼうそう)、日本脳炎、不活化ポリオワクチン、子宮頸がん予防ワクチンは、指定医療機関で個別接種を実施しています(子宮頸がん予防ワクチンの指定医療機関は、このページ最下部の添付ファイルにあります)。
予防接種の最終的な選択は、保護者に任せられています。市から送付している予防接種の説明などをよく読み、予防接種について理解を深めた上で、判断してください。複数の予防接種の同時接種は、医師が必要と認め、かつ保護者が希望した場合可能です。ただし、子宮頸がん予防接種は他の予防接種と同時接種はできません。また、「予防接種と子どもの健康」の中で予防接種を受けることができない場合に該当する人は受けられません。
長期療養により予防接種が受けられなかった子どもに対する特例
長期にわたり療養を必要とする病気で対象年齢までに予防接種を受けられなかった子どもには、治癒後2年間の特例制度があります(医師の指示により接種が不可能な期間が、予防接種の対象年齢全般あった子ども)。対象になる疾患などは細かく定められています。詳しくは担当へお問い合わせください。
対象者および接種方法
対象年齢の考え方:例「出生○週○日後」とは、出生日の翌日を0週1日として算出した日を表します。年齢計算法を用いると7歳6カ月未満は、7歳6カ月になる前日です。
各予防接種ワクチンの定められた接種間隔は、効果的に免疫をつけるためにお勧めする間隔です。
体調が悪く接種できない場合、延長が可能ですができるだけ接種間隔を守ってください。ただし、接種間隔を短くすることはできません。
予防接種健康被害救済制度
定期接種を受けたことにより、重い副反応(健康被害)が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。対象となる健康被害は、厚生労働大臣が予防接種との因果関係があるまたは因果関係がある可能性が高いまたは通常の医学的判断では他の要因も考えられるが因果関係が否定できないと認めた場合に限ります。
予防接種副反応
保護者の方は、定期の予防接種後に発生した健康被害について、必要に応じて報告する制度(厚生労働省報告様式)があります。詳しくは担当へご相談ください。
予防接種助成金制度
平成28年4月1日から医学的な事情や、里帰りなどの市がやむを得ないと判断する事情で、委託医療機関以外での接種を希望する方に、予防接種費用を所定の限度額まで助成する制度です(医学的事情とは重い病気により大学病院などに通院・入院をしている場合を指します)。
制度の利用は事前に申請が必要になりますので、必ず担当へお問い合わせください。
予防接種再接種事業助成金交付制度
令和3年4月23日から、骨髄移植、化学療法等の医療行為により、当該骨髄移植等の前に受けた予防接種法に基づく定期の予防接種による免疫が低下または消失した20歳未満の方に、任意で再度予防接種を受けるための環境を整備するため、再接種費用を所定の限度額まで助成する制度です。
制度の利用には、事前に申請が必要になりますので、必ず担当へお問い合わせください。
乳幼児の予防接種
ロタウイルスワクチン
法律による対象年齢
- 2回接種 出生6週0日後から24週0日後まで
- 3回接種 出生6週0日後から32週0日後まで
標準的な接種期間(望ましい年齢)
初回接種を、生後2カ月から出生14週6日後まで
※安全性が確立されていないため、15週0日後以降はお勧めしていません。
標準的な接種方法
- 2回接種
4週間以上の間隔をおいて、2回経口接種(投与)します(24週0日後までに2回接種終了できること)。 - 3回接種
4週間以上の間隔をおいて、3回経口接種(投与)します(32週0日後までに3回接種終了できること)。
※腸重積症にかかったことがある方、先天性消化管障害の方(治療中の方)、重症複合性免疫不全症の所見がある方は対象外です。
※ロタウイルスワクチンは、出生15週0日以降の初回接種については安全性が確立されていないため、出生14週6日後までに初回接種を完了することが望ましいとされています。
※ロタウイルスワクチンの種類を途中で変えることはできません。
※接種(投与)後、ワクチンを吐き出したとしても追加の接種(投与)は必要ないとされています。
小児用肺炎球菌ワクチン
法律による対象年齢
2カ月~5歳未満
標準的な接種方法
- 生後2~7カ月未満で開始
4週間以上の間隔で3回接種の後、1歳が過ぎていれば3回目から60日以上空けて1回追加接種 - 生後7カ月~1歳未満で開始
4週間以上の間隔で2回接種の後、1歳を過ぎていれば2回目から60日以上空けて1回追加接種
初回2回目の接種は、1歳未満までに行う。 - 1~2歳未満で開始
1回接種後60日以上空けて1回接種 - 2歳以上5歳未満
1回のみ接種
小児肺炎球菌やヒブワクチンは標準的な接種方法で1歳までに接種が終了しなかった場合は、接種回数が異なりますので注意してください。
※Hibワクチンは、製造の初期段階でウシの成分が使用されていますがその後の精製工程を経て製品化されています。これらのワクチンの接種が原因でTSE(伝達性海綿状脳症)にかかった報告はありません。したがいまして理論上のリスクは否定できないものの、このワクチンを接種されて人がTSEにかかる可能性はほとんど無いものと考えられます。
20価ワクチンについて
令和6年10月1日から20価小児肺炎球菌ワクチンが定期接種化されます。
13価、15価ワクチンよりも有効性が期待され、肺炎球菌感染症の原因血清型を幅広くカバーし、肺炎球菌感染症をより広く予防することができます。
交互接種について
13価ワクチンで接種を開始した方は、20価ワクチンへ切り替えて接種した場合も安全性、有効性が認められています。
15価ワクチンから20価ワクチンへ切り替えて接種した場合の安全性・有効性は確認されていないため、15価ワクチンで接種を開始した場合は、原則として15価ワクチンで接種を完了させます。
B型肝炎
法律による対象年齢
生後~1歳未満
※座間市の開始は2カ月からです。
標準的な接種方法
- 2回目 1回目から4週間以上空けてから接種
- 3回目 1回目から20週間以上空けて1回接種
母子感染予防のために、抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンの接種を受けている子どもは、定期接種の対象外です。
参考リンク
5種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)
法律による対象年齢
生後2カ月~7歳6カ月未満
標準的な接種方法
- 初回 3週間から8週間隔で3回接種
- 追加 初回3回終了後6カ月以上空けてから1回
4種混合ワクチン(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)とヒブワクチンを混合した5種混合ワクチンが令和6年4月1日から定期接種となりました。
4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
法律による対象年齢
生後2カ月~7歳6カ月未満
標準的な接種方法
- 初回 3週間から8週間隔で3回接種
- 追加 初回3回終了後1年以上空けてから1回
※5種混合を接種する方は不要
ヒブワクチン
法律による対象年齢
2カ月~5歳未満
標準的な接種方法
- 生後2~7カ月未満で開始
4~8週間隔で3回接種の後7~13カ月に1回追加接種 - 生後7カ月~1歳未満で開始
4~8週間隔で2回接種の後7~13カ月に1回追加接種 - 1歳以上5歳未満
1回のみ接種
※5種混合を接種する方は不要
BCG
法律による対象年齢
出生後~1歳未満
標準的な接種方法
5~7カ月
平成30年11月26日から日本薬局方に適合した新しい添付溶剤(生理食塩液)を用いたワクチンを使用します。
麻しん風しん
- 1~2歳未満
誕生日になったらすぐに接種 - 小学校就学前の1年間
小学校就学前1年前(年長さん)に該当する子ども
より強い免疫を確保するための追加接種
基本は麻しん風しん混合ワクチンです。保護者の希望により単独接種も可能です。麻しん・風しん両方にかかった子どもはこの麻しん風しん予防接種の対象外です。
令和6年度中に麻しん風しんワクチンを接種できなかった方は、定期接種期間が2年間延長されます。
定期接種の接種期間が令和6年度末で終了する方について、ワクチンの供給不足により令和6年度中に接種できなかった場合、定期接種の期間が2年間延長されます。
対象者
| 第1期 |
令和6年度内に生後24月に達するまたは達した方(令和4年4月2日〜令和5年4月1日生まれ) |
|---|---|
| 第2期 |
令和6年度に小学校就学の前年度(年長児相当)の方(平成30年4月2日生まれから平成31年4月1日生まれの方) |
接種期限:令和9年3月31日まで
水痘
- 1~3歳未満
1回目の接種から6カ月以上空けて2回目を接種
3歳を超えると水痘の予防接種は受けられません。1回目の接種開始の時期に十分注意してください(水ぼうそうにかかった子どもはこの水痘予防接種の対象外です)。
参考リンク
日本脳炎
法律による対象年齢
6カ月~7歳6カ月未満
※座間市の開始は3歳からです。
標準的な接種方法
- 初回
3歳から
1週間から4週間隔で2回接種 - 追加
4歳から
2回目終了後、6カ月以上空けて1回接種(お勧めは、おおむね1年空けます)
参考リンク
日本脳炎予防接種に関する詳しい説明、副作用などについては、厚生労働省ホームページの「日本脳炎」をご覧ください。
小学生の予防接種
二種混合(ジフテリア・破傷風混合)
法律による対象年齢
11~13歳未満
望ましい年齢
11歳
備考
対象者へ個別通知を行います。
日本脳炎 2期
法律による対象年齢
9~13歳未満
望ましい年齢
9歳以上10歳未満
備考
対象者に個別通知を行います。2期の接種は1期3回接種後、通常5年間空けて接種してください。
日本脳炎の特例
特例を受けられる対象年齢
平成7年4月2日生~平成19年4月1日生まれで20歳未満の方
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がん予防)ワクチン
HPVワクチンは、令和4年4月から積極的勧奨を再開しています。
また、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人(平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性)で令和4年4月1日~令和7年3月31日までに少なくとも1回以上HPVワクチンを接種した人は、特例措置として令和8年3月末まで従来の対象年齢を超えて公費で接種を行うことができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
他の予防接種との間隔
先に接種したワクチンの体内での活動を他のワクチンが邪魔しないように、間隔をあけて接種することとなっています。
注射の生ワクチンの次に注射の生ワクチンを接種する場合
【注射の生ワクチン】
BCG、麻しん風しん混合、麻しん・風しん、水ぼうそう、おたふくかぜ
↑↓ 4週間あける
【注射の生ワクチン】
BCG、麻しん風しん混合、麻しん・風しん、水ぼうそう、おたふくかぜ
注射または経口(投与)の生ワクチンの次に不活化ワクチンまたは経口(投与)の生ワクチンを接種する場合
【注射の生ワクチン】
BCG、麻しん風しん混合、麻しん・風しん、水ぼうそう、おたふくかぜ
【経口(投与)の生ワクチン】
ロタウイルスワクチン
↑↓ 間隔の規定なし
【不活化ワクチン】
ヒブワクチン、小児用肺炎球菌、4種混合(百日咳ジフテリア破傷風ポリオ)、B型肝炎、日本脳炎、ジフテリア破傷風(二種混合)、不活化ポリオ、インフルエンザなど
【経口(投与)の生ワクチン】
ロタウイルスワクチン
必ず間隔を守って受けましょう。なお、同じワクチンの場合は、各予防接種の接種方法通りです。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども家庭課 こども保健係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7225 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。